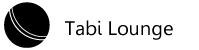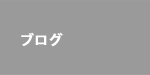2012年06月
 今日はテルアビブに行きたい。朝起きてコーヒーとパンをほおばり、支度をする。
今日はテルアビブに行きたい。朝起きてコーヒーとパンをほおばり、支度をする。
ユダヤ教徒にとって、毎週金曜日の日没前から土曜の日没後までは安息日、シャバットなので、その間はだいたいのユダヤ系交通機関はぴたりとお休みする。アラブ系バスは動いている。
アラブ系バスに乗ってダマスカス門まで行き、そこから休みの路面電車の線路に沿ってセントラルバス・ステーション近くの乗り合いタクシー乗り場まで歩く。黒服のユダヤ人も歩いていれば、タンクトップでジョギングをしている人々もいる。
テルアビブへ向かう通常のバスはユダヤ系のバスなので、走っていない。代わりに、乗り合いタクシー、シェルートに乗っていく。エルサレムはイスラエルの真ん中に位置している。テルアビブは西側にあって地中海に面している。この距離を1時間もかからずに到着してしまうのだから、イスラエルが四国ほどの大きさだということが分かる。
バンから降りると、ターミナル付近には、アジア系の人々の他に、アフリカ系黒人の人々をよく見かけた。テルアビブに多いはずの白人はほとんど見ない。彼らは、エチオピアやスーダン、南スーダン、それにエリトリアといった国々から難民としてやってきた人々で、この5年ほどで増えたのだという。
エジプトから砂漠を歩いて渡り、イスラエルに入ってきたのだと聞く。今は砂漠にフェンスがないのだそう。高い壁をパレスチナ自治区との間につくりあげているイスラエルの砂漠にまだフェンスがない。
イスラエルの男性は渋い顔で言った。「今フェンスを作ろうとしているところだけど、国として今は難民は受け入れざるを得ないんだ。」
ロスチャイルド大通りに面したカフェ、MAX BRENNERチョコレートバーに腰掛けて、ベネズエラのカカオからつくったミルクチョコレートのホットドリンクをオーダーする。チョコレートは「ハグマグ」という独自の器に入れて出される。この「ハグマグ」というのは、チョコレート・セレモニーに使うために生み出されたというから洒落ている。
辺りにはオープンテラスのカフェが並び、マクドナルドも黄緑色ののれんをつけている。並木道は太陽の日差しを受け、ホウオウボクの赤い花が緑に鮮やかに色を添えている。
テルアビブの現代建築群は世界遺産に登録されている。1920年代末から、バウハウスなどの建築学校を卒業した建築家たちがヨーロッパから帰郷したり、あるいはナチスを逃れてこの地にやってきて、街の中心にインターナショナルデザインの建築をつくりあげていった。
ロスチャイルド大通りの建築を、Yona Wisemanさんという女性が紹介してくれるツアーに参加することにする。
一連の建築群が世界遺産に登録されるとなったとき、テルアビブ市民は、ただの古びた建物で、もうすぐ崩れそうな建物もあるのになぜ、と首をかしげたらしい。それでも、最近では価値が見直されてきたのだそう。
テルアビブは街の中心にインターナショナルスタイルを取り入れて膨らんでいったこともとても稀有なことだという。バウハウスの影響を受けた建築物が街全体の6、7割を占めている。
海外からの移住者の増加を可能にした、鉄やコンクリートを使った機能的な建築、アール・デコ様式を取り入れた建築、ゆるやかな曲線を描くベランダ、細く長い直線的な窓、テルアビブが「白い街」と呼ばれるほどのホワイト・トーン。
ツアーを終えて、都市空間デザインで知られるディゼンゴフ広場まで歩く。テルアビブを網羅するレンタサイクルを、地元の若者たちも颯爽と乗りこなしていく。1992年まで映画館として使われていた建物が、今ではホテル・シネマというホテルになっている。
街の通りには、水着を着た人々が歩いている。
黒服づくめの人々も歩いているエルサレムと同じ国で。
地中海につきあたる。そこは明るい日差しの照りわたる、明るい海だった。むわりとする暑さの中で、海岸にはネスレやカールスバーグといった企業のパラソルがびっしりと並び、その下で人々は寝そべったり、あるいはおしゃべりをしたり、水たばこを吸っていたりする。イスラムの黒いアバヤをかぶる女性もいる横で、ビキニを着た女性がシャワーを浴びている。
海辺の売店でユダヤの伝統的なパンだともいわれるベーグルを買い求める。ごまののったベーグルを2つにスライスし、ピクルス、トマト、オリーブ、玉ねぎ、コーン、それにスライスチーズをのせて焼く。香ばしく、中はもっちりとして、とけたチーズと具材がよくからまりあっている。
海岸沿いに海を右手に眺めながら、歴史ある地区、オールド・ヤッファまで歩いていく。左手には、無機質な高層ビルが立ち並び、非現実的な趣をみせている。海はあくまで明るいままだ。
オスマン帝国時代につくられた時計台の周りには、アラブ系のスイーツ屋やサンドイッチ店などが軒を連ねる。丘の上からはテルアビブの街並みが一望できる。空には飛行機が飛び、海にはヨットが浮かんでいる。1880年代から90年代にかけて建てられた聖ペテロ教会や、願いがかなうという橋を抜けて、煉瓦づくりの小道Netiv Hamazalotを進むと、小さな港に出る。
港の近くのカフェのテラスで人々はくつろぎ、食事やお酒を楽しんでいる。Gold Starというダークラガービールをオーダーする。苦いけれど、軽いビールだ。
日も暮れて、シャバットが終了した。これで、20時以降、エルサレムまでのバスが運行が再開する。
灯のともる道をたどりながら、バスターミナルまで行こうとNeve Tsedek地区に立ち寄りながら歩く。この地区は、19世紀にはユダヤの知識人の住んでいたが、今では裕福な若者やアーティスティックな人々の住むエリアとなり、お洒落なカフェやレストラン、陶器屋などが並んでいる。
ふいにイスラエルの女性が、流暢な英語で道案内をしてくれると言った。アイスクリーム屋で働いている女性で、仕事のあと、疲れた身体で見送ってくれる。
テルアビブは夜まで賑やかだった。夜の遅くまで交通機関が動いている。22時に、これからエルサレムまで戻りたいと地元の人々に言っても驚かれない。エルサレムまでこれから戻るのね、じゃあ、バスの時刻表を調べてみるわね、とiPhoneをさくさくいじり、最終バスの時間まで教えてくれるほどである。
こうして途中からバスに乗ってターミナルまで行き、ごまつきベーグルを買い求めて、乗車する。定刻の22時45分に発車したバスでベーグルをほおばりながら、エルサレムへと戻る。ちょうど1時間でエルサレムにたどり着き、まだ人々の多く乗車する路面電車に乗って、そこからオリーブ山を登って家に帰る。オリーブ山のてっぺんには、いつもの通りにイスラエルの旗がライトアップされてたなびき、ユダヤ人墓地は岩のドームを向いて、ずらりと並んでいる。
紅茶にご飯、野菜にじゃがいもやにんじんの煮物、それに林檎をかじって休むことにする。
2012/06/16 23:43 |
カテゴリー:Israel & the Palestinian Territories
 朝食にチキンやスクランブル・エッグ、ピザ、それにじゃがいも、グリーンピースとにんじんの煮物をいただいてから、イブラヒムさんのご飯づくりを手伝う。
朝食にチキンやスクランブル・エッグ、ピザ、それにじゃがいも、グリーンピースとにんじんの煮物をいただいてから、イブラヒムさんのご飯づくりを手伝う。
レモネードを飲みながら、にんじんもじゃがいももどっさりと袋から出して大きな鍋に放り込む。イブラヒムさんはにんじんの皮むきも手元を見ずにすぱすぱ切っていく。それを見てみてとばかりに得意顔をこちらに向けるのだから、茶目っけがある。
今朝はイスラエルのユダヤ人数百人分の料理を作っていると言った。数百人分なんて大した量じゃないよと言った。彼にとっては、民族も国籍も宗教も関係ないのである。
イブラヒムさんの家のあるオリーブ山は、終末の日が訪れるとメシアが立ち死者がよみがえるといわれている場所で、岩のドームを眺めるようにずらりとユダヤ人墓地が並んでいる。ここの墓地はとても高額らしい。
イスラエルは、この山の頂上に国旗をかざすため、もともと住んでいたアラブ人の住人にビルの一部を譲るように交渉をしたという。それに反対したアラブ人住人を、補償金がほしいアラブ人住人が殺したという話も聞いた。
そのオリーブ山の頂上付近にあるイブラヒムさんの家から城壁に囲まれた旧市街まで歩いて30分ほど。イエスが昇天した場所にある昇天教会や主の祈りを弟子に教えたといわれる主の祈りの教会などが途中にあって、立ち寄りながら旧市街へ向かう。
イエス・キリストは、有罪判決を受けて、十字架を背負って処刑が行われるゴルゴダの丘まで歩いた。その足跡をなぞり、毎週金曜日午後には旧市街のヴィア・ドロローサと呼ばれるその道をフランシスコ派の修道士が行進する。道なりには14の祈祷所が設けられていて、それぞれのステーションで、イエスにおこった出来事についての祈祷文が読み上げられる。
ヴィア・ドロローサは当時から繁華街で、今もたくさんの土産物屋が軒をつらねている。その中で修道士が祈祷文をマイクで読み上げ、それが終わるとみなで賛美歌を合唱し、次のステーションへと向かう。
イエスが死刑の判決を受けた場所から始まる。十字架を背負い、鞭でうたれ、一度つまづく。聖母マリアがそのイエスを目にし、キレネ人のシモンがイエスを助け、ベロニカがイエスの顔をふき、イエスは再び倒れる。それからイエスはエルサレムの女性たちに語りかけ、三度目に倒れ、衣服をはぎとられられる。十字架がたてられ、イエスは息をひきとり、聖母マリアが遺体を両手で受け止める。そして最後に、墓に向かう。
世界各地のキリスト教徒たちが、祈りを捧げにやってきている。ろうそくを灯し、想いをはせ、イエスの墓に列をつくる。イエスが息を引き取ったあとに香油を塗られた場所で膝まづき、手をのせ、頭をつける。チーンと鐘の音がして、聖職者は香炉を振り、鳩は飛んでいく。
そのうちにそれぞれがばらばらになり、ミサが始まっていく。
 ユダヤ教徒にとって、毎週金曜日の日没前から土曜の日没後までは、安息日、シャバットだ。神が天地創造の7日目に休んだことにちなみ、この間は心も身体も休めなければならない。
ユダヤ教徒にとって、毎週金曜日の日没前から土曜の日没後までは、安息日、シャバットだ。神が天地創造の7日目に休んだことにちなみ、この間は心も身体も休めなければならない。
手荷物検査を受けて入るユダヤ教徒の嘆きの壁には、シャバットに入る金曜夕方、多くのユダヤ教徒が集まる。
イスラエルの国旗がたなびき、左手が男性、右手が女性の部分と、仕切りが設けられている。子どもたちも男女に分かれるので、黒い正装を着たユダヤ教徒の男性が、男の子をのせたベビーカーを押していたりする。
男性が頭にかぶる帽子キッパや、女性が肌を覆うスカーフも貸し出される。聖書や、金曜の夜&フェスティバルのための祈りの本、The Kotel Siddurという本などが本棚にずらりと並び、だれしもが手に取れるようになっている。
男性のほうは、ラーララライライライとリズムをつけて、肩車をしながら、腕をくみ、手をふりあげ、あるいは手拍子をしながら、ぴょんぴょんと踊りだす。そうして踊っているのは大抵頭の上に白いキッパをちょこんとのせた人々で、まるでスポーツ観戦のようにはしゃぐようすで嘆きの壁に背を向ける人もいる。
超正統派のユダヤ教徒は、くるくるとしたもみあげを長く伸ばし、豊富な髭をたくわえ、黒いハットやファーの帽子をかぶり、黒いコートを着ている。こうした人々は、それを横目に粛々と壁に向かっている。聖書を片手に、身体を前後や左右に揺らしながら、ときには声をあげて謡うように祈る。暑いのか、汗をかいている。顔に笑顔は、ない。
女性も同じように輪をつくり、腕をくんで、歌い、踊り始める。黒い服を着た幾人か女性たちは聖書を片手に、あるいは顔につけて壁に向かっている。願いや祈りを小さな紙切れに書いて壁の隙間にはさんで、祈りを捧げる人もいる。仕切りの向こうの男性たちの様子を外から眺める女性もいる。
男女の中には軍服を着た人々もまじっている。
シャバット中は、何もしてはいけない。電気機器を利用することも、ものを書くことも許されない。
日もとっぷりと暮れていく中、照明のつく嘆きの壁の前はより盛り上がりをみせていく。20時半を過ぎたころに、徐々に人々は家路につく。
そのころには嘆きの壁の近くのユダヤ人街はほんのわずかなユダヤ人が歩くばかりで、その他は、猫が橙色の灯にともされた通りをするりと抜けていくばかりだ。
そんなユダヤ教にとっての金曜日夜でも、アラブ系バスは運行している。空には花火があがる。家に帰って、じゃがいもやにんじん、いんげんの煮物やカリフラワー、それにパンやごまのペースト、レモネードをいただいて休むことにする。
2012/06/15 23:40 |
カテゴリー:Israel & the Palestinian Territories
 朝の4時になるころ、アザーンが爆音で町に鳴り響く。
朝の4時になるころ、アザーンが爆音で町に鳴り響く。
イブラヒムさんが今日は朝から家にいた。イブラヒムさんの口癖は、WELCOMEとEATとFOODである。大声で腹の底からそう口にする。そして、鍋たっぷりにいつも豪快な料理をしてくれる。
朝食は、パンにコーヒー、それからじゃがいもやにんじん、グリーンピースの煮込みをいただく。
イブラヒムさんのお父さんの時代から始めたピースハウス、受け継いで50年。ホワイトハウスにも呼ばれ、各国に「友だち」がいる人だ。国籍は、ない。パスポートも、ない。それでも各国に呼ばれるから出向いていく。
パレスチナ系イスラム教徒であるイブラヒムさんが、イスラエルの国籍を取得することはない。国籍を取得するということは、抑圧する側の立場にたつことを意味するからだ。
イブラヒムさんは、お金は世界中に十分あるのに、それが正しい場所に使われていない、と言った。
たとえば、ある人が他人のカメラを盗みます。たいていの人は、怒る。でも、その盗んだ人は、自分の赤ん坊にミルクをやる必要がある。だから、そのミルクを与えてやれなかった人々の責任でもある。盗んだ人が、なぜ盗んだのかを考えなくちゃいけない。腹が減った人の口にパンを入れてやらなきゃいけない。
キリスト教、イスラム教、ユダヤ教も仏教も関係ないと強調する。人は宗教などを額に書いていない。わたしたちはみな一つなんです。
70歳だという、背の高くないイブラヒムさんは、それでも体格がよく、太くて柔らかい指を持っている。僕は小さくて髪もない男なんだと、かぶっていたカフィーヤをするりと取る。イブラヒムさんのかぶるカフィーヤは、パレスチナ人を意味する白と黒ではなく、遊牧民族ベドウィンのかぶる赤と白色だ。
脚を痛めて薬をぬりながら、それでも3台の携帯を両手に抱えている。一人と話している間に、もう一人と話す。そう慌ただしくしているうちに、頭をがんがんと壁にぶつけて、こんな携帯、もうあげるよ、と冗談を言う。
イブラヒムさんは、今、岐路に立たされている。ピースハウスを守るために別に建てた家が、高額にすぎる建築許可書を取得せずにいたものだから、法廷に呼び出され、多額の罰金を支払い始めている。そしてこのピースハウスが寄付で賄われていることから課税対象になるというので、それもまた問題になっている。罰金の支払いが滞れば、家は壊され、投獄される。その立ち退き費用も、立ち退く際の見張り軍人の費用も、イブラヒムさんの負担になるという。涙を流すイブラヒムさんの姿もあったと聞く。
それでもイブラヒムさんはI love people、と言った。そして、じゃがいもを大量に鍋にいれて茹ではじめる。そのうちに、取材を受け始める。滞在していたロシア正教の女性は支払うお金が無い、と言う。イブラヒムさんは、お金を工面しようとする。
12時を過ぎて、パレスチナ自治区にあるベツレヘムに向かうことにする。
チェックポイントを通らずにベツレヘムへ入る21番のバスにはトルコ国旗が掲げられ、アラビア文字が書かれている。このバスが、ユダヤ系ではなく、アラブ系のバスであることを意味する。きれいに舗装された道を進んでいく。1時間と少しでベツレヘムの町に着く。パレスチナの車とイスラエルの車で、違うナンバープレートの色がはられて走っている。
食堂に入り、ひよこ豆のペースト、フームスをオーダーする。トマトとピクルスとパン、それにターメイヤがついてくる。
町の中心であるメンジャー広場の片隅には、パレスチナの土地が1946年から段階を経て、ユダヤ、イスラエルの土地に変わっていった様子を地図に示している。そして、チェックポイントや分離壁についてもまとめて語っている。
ベツレヘムには、イエス・キリストが生まれたとされる聖誕教会がある。「謙虚のドア」と呼ばれる小さな入口をくぐると、天井から多くのランプがぶらさがっている会堂に入る。床にはコンスタンティヌス帝のころのモザイクが残されている。聖職者が歌を歌い、鐘をならし、お香を振って歩く。
階段を下りて洞窟の中に入っていくと、キリストが生まれたとされる場所に、銀の星が埋め込まれた祭壇があり、ろうそくに火がともされている。人々が列を作ってその場所に口づけをしていく。
すぐ北には、クリスマスのミサが有名なフランシスコ派修道院聖カテリーナ教会がある。
そして東には、ミルク・グロットがある。淡い乳白色のその教会は、イエスを見守るマリアの母乳が地面にこぼれ、赤かった地がミルク色に変わったという伝説に基づいている。
警察署には、前アラファト議長と現アッバス議長の写真が飾られている。
道には Star & Bucks Cafeがある。緑のロゴのついたマグカップもTシャツも売られている。
聖ヨセフの家であり、現在はシリア・カトリック教会のホスピス付き教会には、女性が集まり、歌を歌っている。丘の上には、ダビデの井戸がある。
商店でチョコとバニラのアイスクリームを買い求めて食べながら歩く。
 ベツレヘムにもまた分離壁がある。分離壁は、イスラエル側が自爆テロの防止のためだと説明する、いまだに建設中の壁だ。パレスチナではこの壁は「アパルトヘイト・ウォール」と呼ばれている。高さ8mという高さの無機質なコンクリートの壁が伸びている。
ベツレヘムにもまた分離壁がある。分離壁は、イスラエル側が自爆テロの防止のためだと説明する、いまだに建設中の壁だ。パレスチナではこの壁は「アパルトヘイト・ウォール」と呼ばれている。高さ8mという高さの無機質なコンクリートの壁が伸びている。
イギリスの画家、バンクシーが描いた絵が色を添える。
らくだに人々が登る絵は、上から白いペンキで消されていた。壁には、「自分の世界をつくるために、他人の世界を殺す」「わたしが大人になったら、レーザービームで壁を吹き飛ばす」「この嘘は長引かない」「パレスチナに自由を」「全世界が見ている」といった言葉が並ぶ。
帰り道は、チェックポイントを通り、帰る必要がある。長い通路を渡り、くねくねとした建物内の道を通る。パスポートがさっと確認される。通勤時など、ここが長蛇の列になることもあるらしく、生活が阻害されている。
建物をでるころには夕暮れが近づいてきていた。バスに乗ってエルサレムに戻る。夕食は、チキンの炭火焼にサラダ、じゃがいもとトマトの煮物にピザ、それにアーモンドジュースをいただく。
2012/06/14 23:52 |
カテゴリー:Israel & the Palestinian Territories
 イスラエルのイミグレーション・オフィスのある新しい建物の前には長蛇の列ができていている。細かな水を吹き付ける装置が置かれ、人々をわずかに濡らしながら、涼ませている。
イスラエルのイミグレーション・オフィスのある新しい建物の前には長蛇の列ができていている。細かな水を吹き付ける装置が置かれ、人々をわずかに濡らしながら、涼ませている。
大きな荷物と小さな荷物に分けて荷物チェックが入る。まず大きな荷物を預ける。すると窓口でパスポートの裏に荷物検査のシールがぺっとりと貼られる。小さな荷物は、別に手で持っていき、X線にかける。
そこから、「外国人」「パレスチナ」「東エルサレム」とに分けられる。イミグレーションの窓口へと進み、幾度も「スタンプは別紙に」と前のめりに伝える。
パスポートには、スタンプを押さないでください。
イスラエルへ入国したことが分かると、これから訪ねるアラブ、イスラム国で入国を拒否されるときがある。だから、イスラエルの入出国スタンプを、パスポートではなく別の紙に押してもらうように強くお願いをする必要があるのだ。
キング・フセイン橋の担当者たちは「スタンプは別紙に」と言われることに慣れている。でも「スタンプは別紙に」とお願いをしても、とくに明確な基準もなく担当者によって旅行者たちの切実なお願いを却下してパスポートにスタンプを押してくる人もいるようで、全く困ったものである。
こうして、それぞれ職員と旅行者の間で心理戦が繰り広げられるのである。
茶目っけのある担当職員は、少しいじわるそうな笑顔を浮かべて、質問をしてくる。氏名、国籍、宿泊先、渡航場所。パレスチナ自治区の町は口にしない。ただ「エルサレムに行きます」と言う。
宿泊先は予約をしているのか、今そのホテルに電話をしたら、あなたの名前はありますか、と尋ねられる。予約はしていません、だから電話をかけても、わたしたちの名前はありません、と答えると、そうですか、分かりました、とあっさり言われる。
スタンプは無事に専用の別紙に押された。ふう。
そこから、さきほど預けておいた大きな荷物を受け取る段になる。空港のようにベルトコンベアにのせられて、ぐるぐると回っている。わたしたちの一方は荷物検査だといって別室に連れて行かれ荷物の所持者であることが確認できると、あっさりと通過できた。
なのに、もう一方の荷物がなかなか出てこない。こうして荷物の出てこない人たちが、ある人は既に3時間以上待たされているといい、職員に向かって怒りの声をあげている。それでも職員は、ただ「待ちなさい」と聞く耳をもたない。なにを言っても、なにを聞いても、「待ちなさい」。
放置されたまま、時間が過ぎてゆく。
ベルトコンベアにのせられていない荷物は、結局荷物検査の別室に積まれていた。1時間ほど待ったところで、3時間以上待った人々とともに別室に連れて行かれる。
すると、荷物に軽く触れられただけで、問題ないから行っていい、と言う。3時間以上待った人々も同様で、ひたすらに待たされた時間は何だったのだとみな首をかしげている。
このわけも分からず放っておいて時間を浪費させるスタイルは、全国にある「チェックポイント」ではよくある話らしい。
とにもかくにも荷物を受け取り、両替をしてエルサレムまでのバスに乗り込む。
エルサレムまでの道の途中に検問が一度ある。銃をもった若い女性がバンに乗り込んでパスポートの確認をする。その他は問題もなく舗装された道を走り続ける。
国境から50分ほどでエルサレムに到着する。近い。暑かったので、ジューススタンドに立ち寄り、ベリーのフローズンジュースをごくりとやる。
ここには、肌を出した洋服を着る女性もいる。
多くの人々が英語を流暢に話す。
路線バスも新しく、寒いほどの冷房がついている。
お世話になるPeace House、イブラヒムさんの家にお邪魔する。ここは、イブラヒムさんというおじいさんが、寄付制でご自宅だった場所を広くみなに提供しているお家である。
今日イブラヒムさんは、イスラム教のスフィーの人々とミーティングをするためにハイファに行っているというので、メキシコ系アメリカ人だというアーネストさんが代わりに迎えてくれ、食事を温めてくれ、コーヒーを淹れてくれた。じゃがいもやにんじん、グリーンピースの煮物に、炊きこみご飯、それにパンにコーヒー、お腹いっぱいだ。
アーネストさんは、アメリカには気持ちの面でいられなくなって、一連のイスラエルで起きている問題を知ろうと思ってやってきた、と言う。
イブラヒムさんの家は、オリーブ山の頂上近くにあり、屋上からは街並みを望むことができる。すっかり日が暮れて灯りのともる街並みを、屋上から眺める。分離壁やモスク、教会の灯りが見え、花火が上がる。
2012/06/13 23:10 |
カテゴリー:Israel & the Palestinian Territories
ヨルダンのアンマンから、キングフセイン橋を通って、イスラエルのエルサレムへ抜けるルートです。
1.アンマンのムジャンマ・シャマーリー・バスターミナルから、キングフセイン橋行きのセルビスに乗る。
(※所要1時間。 JOD 6.00)
2.キングフセイン橋に到着後、ヨルダン側で出国手続。出国税JOD 8.00を支払う。
出国カードを記入。パスポートと一緒に提出。
(※何も言わなくても、パスポートにスタンプは押されませんでした。)
3.手続後、イスラエル側国境に行くバスに乗車。
(※荷物代込みで、JOD 5.13)
4.10分程で、イスラエル側国境に到着。
5.大きな荷物を、係員に預ける。
(※預ける際、パスポートにシールが貼られます。
このシールの跡がパスポートにあるだけでも、イスラム諸国では入国を拒否する場合 があるそうです。対策として、①パスポートカバーをつけておくと、パスポートカバーに シールが貼られるので、大丈夫 です。②シールが貼られた後、すぐはがして、も う一度貼ると、はがれやすくなり、跡が残りにくくな るようです。)
6.入国審査を受ける。
(※この際、イスラエルの後に、イスラム諸国へ行く可能性がある人は、パスポートを提出する前に、別紙にスタンプを押してもらうよう、係官に伝えてください。その際、いくつか質問を受けます。かなりがんばらないと別紙に押してくれない係官もいるようです。)
7.荷物を受け取る。
(※荷物が検査になる場合があります。その際は、別室の検査室に行き、荷物の中身の確認を受けます。私は別室に行きましたが、特に開けられることなく、済みました。が、相方の荷物が中々出て来ず、長時間待たされてしまいました。結局相方の荷物は検査の対象になっていないにも関わらず、荷物検査室に置き去りになっており、誰も気づかなかったのが原因です。)
8.エルサレム(※ダマスカス門)行きのバスに乗る。
(※所要1時間。NIS 32.00)
◎両替
イスラエル側に両替所があります。
JOD 1.00 = NIS 5.12
2012/06/13 16:00 |
カテゴリー:Israel & the Palestinian Territories, Jordan, ささやかな、旅のじょうほう
« Older Entries
Newer Entries »
 今日はテルアビブに行きたい。朝起きてコーヒーとパンをほおばり、支度をする。
今日はテルアビブに行きたい。朝起きてコーヒーとパンをほおばり、支度をする。